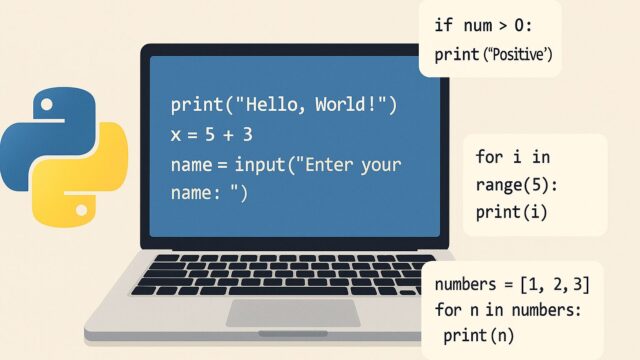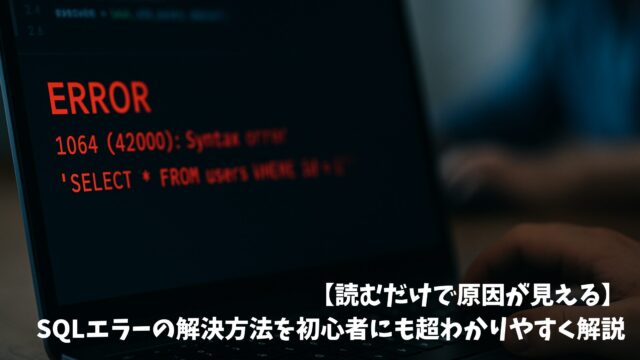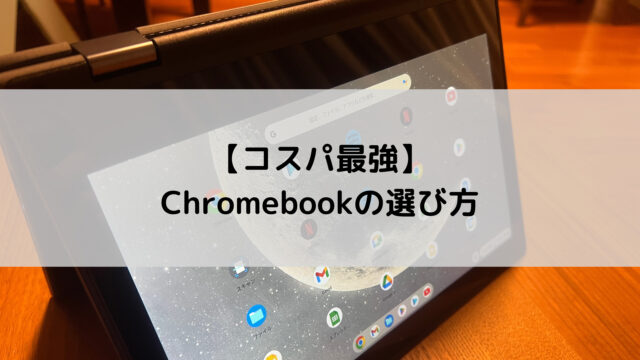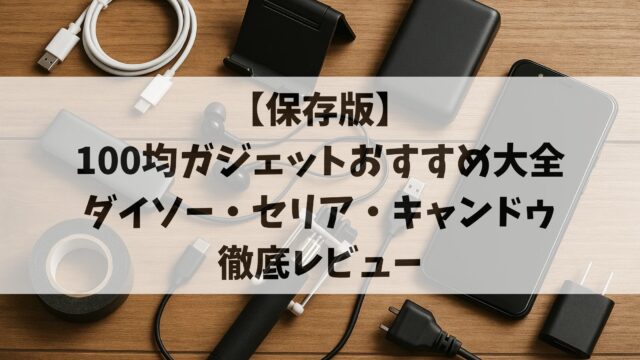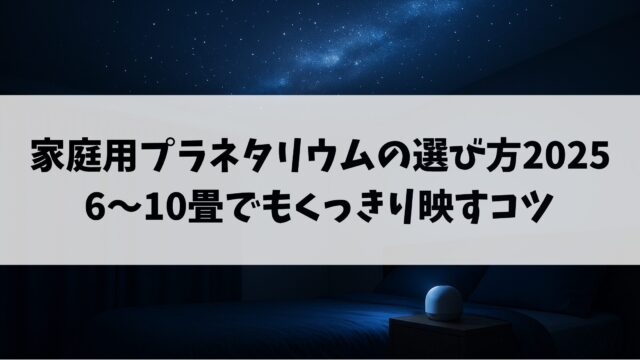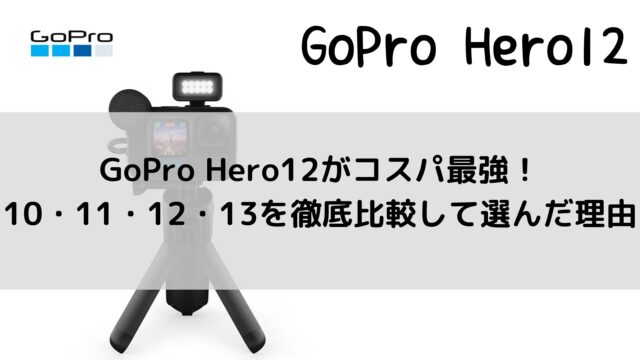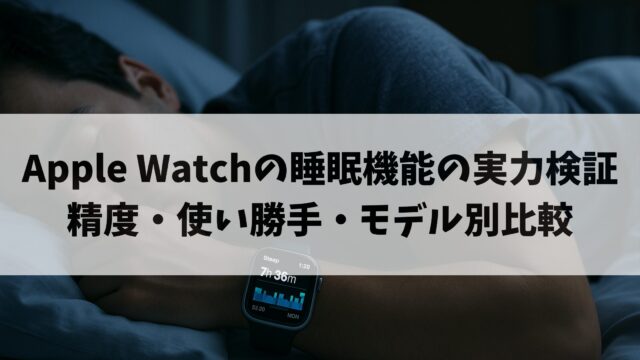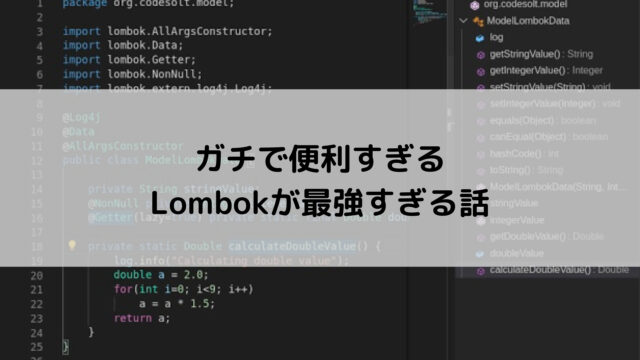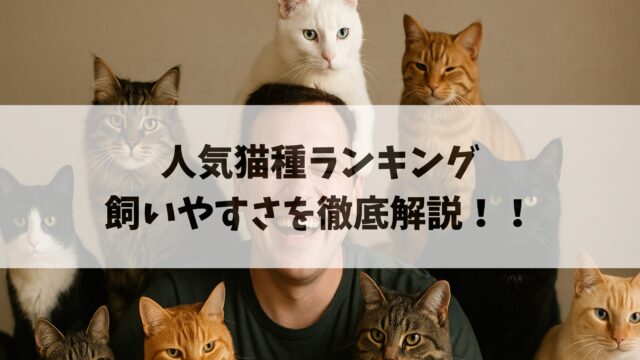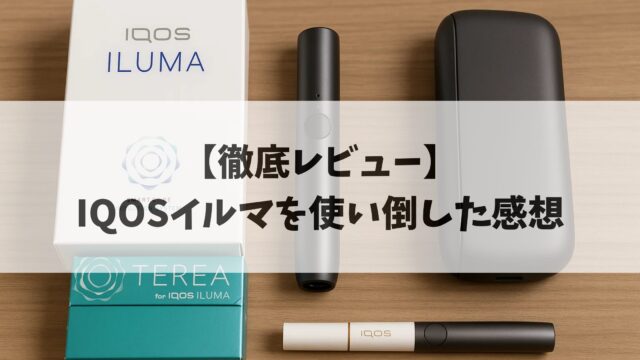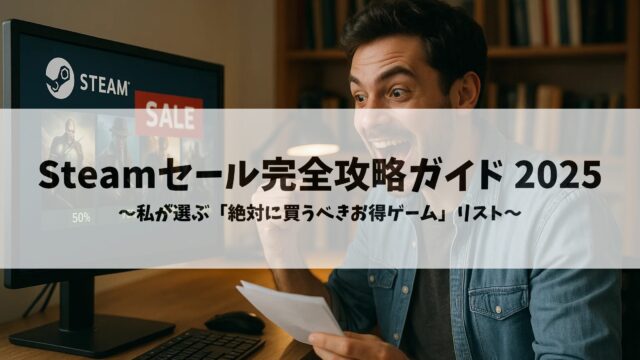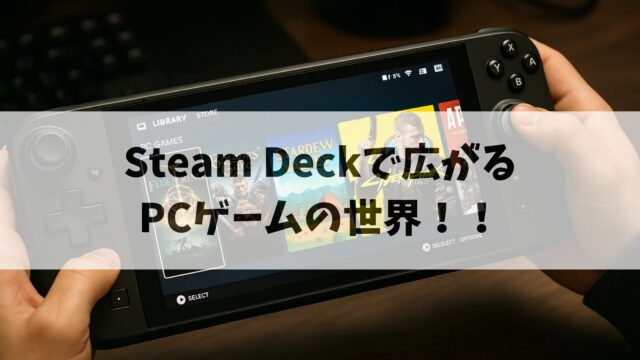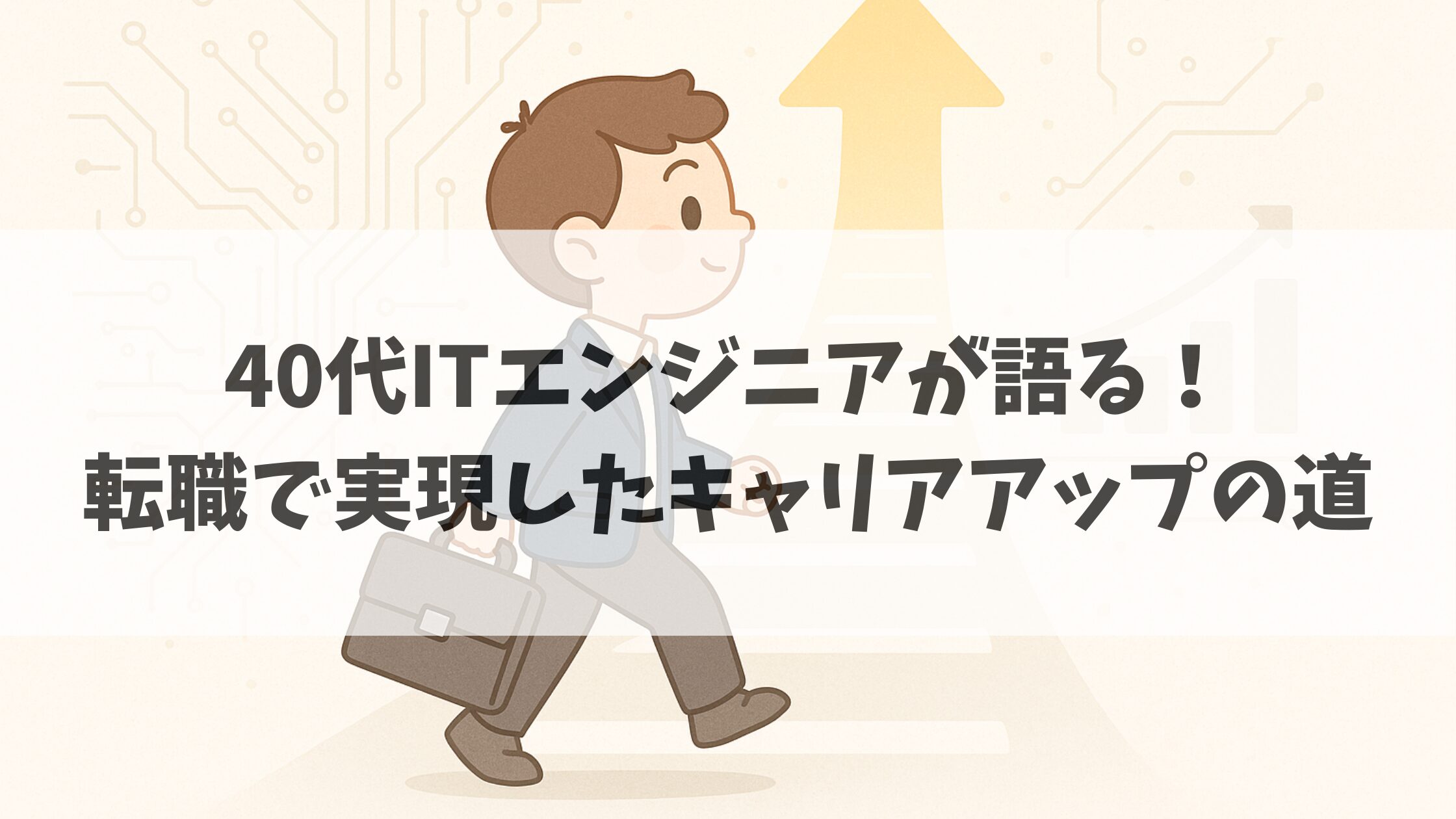40歳を過ぎて、キャリアに行きづまりを感じていませんか?
「これまでの経験をどう活かせるか」「次の転職で失敗したくない」「年齢という壁をどう突破すればいいか」…
本記事では、私が複数回の転職・挑戦を通じて見えてきた”40代以降に強くなるキャリア設計の道筋”を、具体的な戦略と実例を交えて語ります。
読み終えたときには、自信をもって次のステップを選べる視界を手にしているはずです。
はじめに
「40代からの転職は難しい」「SIerから事業会社に移るのはハードルが高い」――そんな声をよく耳にします。
しかし、私は22歳で社会人をスタートしてから、これまでに4回の転職を経験し、現在は通信キャリアのIT部門でシステム開発とAIのR&Dを担当しています。
入社時年収400万円から始まり、今は年収1,100万円まで到達しました。
決して順風満帆ではなく、迷いや後悔もありましたが、その経験から学んだことをまとめることで、これから転職を考えるエンジニアの方に役立つはずです。
この記事では、私のキャリアの歩みを振り返りつつ、転職で大切にすべきポイント、SIerと事業会社の違い、40代からのキャリア戦略について掘り下げます。

この記事を読むことで、あなた自身がキャリアを選ぶときの判断軸が整理され、「やりたいこと × 収入 × 市場価値」の具体的なヒントを得られるはずです!
キャリアサマリー
まずは私のキャリアについてざっと紹介します。
| 会社 | 年齢 | 仕事内容 | 年収(入社→退職) | 退職理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1社目: メーカー系子会社SIer | 22歳-28歳 | 設計以降の工程担当 | 400万→550万 | 下請け体質が嫌で退職 |
| 2社目: 商社系SIer | 28歳-30歳 | ベンダ管理(プライムだが丸投げ感) | 600万→650万 | ベンダー丸投げの仕事に嫌気 |
| 3社目: メーカー系SIer | 30歳-38歳 | 要件定義〜全工程(手を動かすプライム) | 650万→750万 | 事業会社に興味 |
| 4社目: 飲食チェーンIT部門 | 38歳-40歳 | システム開発、IoT/AI PoC | 750万→800万 | コロナで収入減 |
| 5社目: 通信キャリアIT部門 | 40歳-現在 | システム開発、AI業務改善R&D | 900万→1,100万 | — |
各社での経験と学び
1社目:メーカー系子会社SIer(22歳〜28歳)
学び: 基礎的な設計・開発スキル、プロジェクトの流れ
苦しさ: 顧客と直接関わらないもどかしさ
退職理由: 下請け体質から脱したい
2社目:商社系SIer(28歳〜30歳)
学び: ベンダー交渉、契約管理
苦しさ: 技術を自分で磨けない
退職理由: 丸投げ体質への違和感
3社目:メーカー系SIer(30歳〜38歳)
学び: 顧客折衝、要件定義〜開発全般、チームマネジメント
退職理由: 事業会社で働いてみたい
4社目:飲食チェーンIT部門(38歳〜40歳)
学び: ITが事業に直結する感覚、新技術の実装経験
退職理由: コロナで収益減 → 安定性を求めて転職
5社目:通信キャリアIT部門(40歳〜現在)
学び: 安定と先端技術の両立、AIによる業務改善
成果: 現在年収1,050万円
転職で学んだこと
総括
私の5回の転職は「逃げ」ではなく「進化の選択」でした。
基礎を固め、商流を理解し、顧客に向き合い、事業を動かし、安定と挑戦を両立する。
この道のりを通じて、私は「技術もビジネスも事業もわかるIT人材」としての総合力を磨いてきました。
言い換えれば、私は 「現場の泥臭さから経営の視座まで、ITを軸に語れる人材」 になったと自負しています。
だからこそ、これからは「事業を動かすためにITをどう活かすか」をさらに突き詰め、未来につなげていきたいと考えています。
市場価値を意識してキャリアを積む
市場価値=「自分を採用したい企業がどれだけあるか」
意識するメリット: 判断基準が明確になる、交渉力が増す、学び続けられる
高め方: スキルの見える化、成果を数値で示す、需要領域を学ぶ、求人市場を定期チェック

1,2,3社目ですべての工程を経験することができ、上流から下流まですべてができる技術者として、市場価値が大幅アップしたと実感しています!
2社目でベンダー管理ばかりやっていたら、大した市場価値にはならなかったと思うので、本当に転職してよかった!
手を動かすマネージャーの価値
世の中にはマネージャはあふれています。口が達者なマネージャ、人脈豊富なマネージャ、調整力抜群のマネージャ、いずれも立派なことですが、実作業ができるマネージャとはあまりあったことがありません。
私は、実作業もできる、歌って踊れるエンジニアこそが、抜群の市場価値を勝ち取る方法だと思っています!
なぜ大事か
比較表
| 項目 | 手を動かすマネージャー | 管理だけのマネージャー |
|---|---|---|
| 技術力 | 現場で最新技術をキャッチアップできる | 技術から離れ、知識が陳腐化されていく |
| 部下からの信頼 | 「一緒に戦える上司」として信頼されやすい | 「わかってくれない管理者」と思われがち |
| 市場価値 | マネジメント+実務スキルで希少価値が高い | 管理職ポストが減ると代替されやすい |
| 成長機会 | 実務で挑戦できる | 成長機会が限定的 |
| キャリアの柔軟性 | 技術職・管理職どちらも可能 | 管理職以外に戻りにくい |
転職エージェントは絶対に使うべき
私は4回の転職すべてで、転職エージェントを活用しました。結果としてこれが大正解でした。
なぜ使うべきか
- 非公開求人にアクセスできる
転職サイトに出ているのは「表向き」の求人だけ。実は企業の多くは、条件の良いポジションほどエージェント経由で人材を探します。理由は、応募が殺到して処理が大変だから。つまり、エージェントを通さないと見えない“お宝案件”がゴロゴロあるんです。 - キャリア相談と「市場での自分の立ち位置」がわかる
自分では「これくらいの年収が妥当かな」と思っていても、市場価値を正確に判断するのは難しい。エージェントは数多の候補者と求人を見てきているので、「あなたならこの業界でこれくらいが相場」というリアルな目安を示してくれます。言ってしまえば、キャリアのGPSみたいな存在。 - 応募書類や面接のフィードバックがもらえる
履歴書や職務経歴書をただ送るだけでは、企業の採用担当に刺さらないことが多い。エージェントは企業ごとの“好み”を知っているので、「この会社にはこうアピールしましょう」と具体的に手を入れてくれる。さらに面接後には、企業からの本音フィードバックも回収してくれるので、次に活かせるという圧倒的なアドバンテージがあります。 - 年収交渉や条件調整をしてくれる
自分で「もっと年収を上げてください」と交渉するのは気まずいし、失敗すると内定が飛んでしまうリスクもあります。エージェントならプロとしてスマートに交渉してくれるので、希望条件を実現しやすい。つまり「嫌われ役」を引き受けてくれるんです。
見栄を張らないこと
転職エージェントには絶対に見栄を張らないほうがいいです。
- ミスマッチを避ける
希望条件やキャリアの実績を盛ったり隠したりすると、一見チャンスが広がったように見えて、実際には「合わない会社」に紹介される確率が増します。入社した後に「思ってたのと違う…」となるのは悲劇。正直に話せば、エージェントがあなたの本音に沿った“的中率の高い求人”を探してくれます。 - 嘘はすぐバレる
企業の採用プロセスは甘くありません。経歴の誇張はリファレンスチェック(前職への問い合わせ)で露呈するし、スキルの誇張は面接や実技テストで簡単に炙り出されます。エージェントに嘘を伝えてしまうと、企業にも不信感が伝わり、二重のダメージになる。これはまさに“自爆テロ”。正直にしていた方が結果的に安全です。 - 弱点も「戦略的に補強」できる
たとえば「英語は苦手です」「マネジメント経験が浅いです」と正直に伝えれば、エージェントはそれをカバーする戦略を考えてくれます。別の強みを推す、研修や学習プランを勧める、求人をうまく選ぶ――嘘をつかずに弱点を晒した方が、むしろ有利に転ぶことが多いんです。 - 信頼関係が築ける
転職エージェントとの関係は一種の“チームプレイ”。嘘をつくとチーム内の信頼が壊れてしまい、全力でサポートしてもらえなくなる危険があります。逆に、ありのままの状況を話せば、担当者も「この人は信頼できる」と感じて全力で動いてくれる。人間関係の本質は、転職の場でも変わりません。
使い倒すくらいがちょうどいい
エージェントは受け身で使うのではなく、「自分のキャリアを最大化する道具」として使い倒すことが大切です。
- ビジネスモデルを理解すると遠慮無用になれる。
転職エージェントは、あなたが企業に転職を決めることで成功報酬(年収の30〜35%程度)を企業からもらいます。つまり彼らのビジネスは「候補者を転職させる」こと。こちらが相談すればするほど彼らも利益になる。使い倒すことは相手にとってもメリットなのです。 - 自分の手間と時間を圧縮できる
求人サイトで100件の求人を探して、企業研究して、書類を一社ずつ作って送って…そんなことを一人でやっていたら、精神的にも時間的にも消耗します。エージェントを“道具”と割り切れば、「市場リサーチ」「求人ピックアップ」「書類添削」「面接フィードバック」「条件交渉」まで全部外注できる。まるで自分専属の秘書と戦略参謀を同時に雇ったようなものです。 - 遠慮すると転職する気がないと思われ逆に損
エージェントは複数人の候補者を同時に担当します。つまり「使い倒してくれる候補者=本気度が高く、転職成功確率が高い」と判断され、サポート優先度も上がる。逆に遠慮して「まぁ任せます…」なんて受け身だと、他の積極的な候補者にリソースを割かれてしまう。使い倒すほど、向こうも本気になるという逆説です。 - 道具として割り切るからこそ冷静になれる
転職は感情が入りやすいイベント。「この会社いいかも!」と浮かれて冷静さを失うこともある。エージェントを“道具”と捉えて、「客観的な情報源」「条件を調整するレバー」として活用すると、感情に流されにくくなる。つまり、人生の大きな選択を冷静なデータと戦略で進められる。
ITエンジニア転職市場の現状(2025年)
需要は強いが変化期にある
まず、結論から言うと「需要は依然として強い」「売り手市場は続いている」一方で、「条件や選別の厳しさ」「求められるスキルセットの変化」が非常に速く、まさに変化期にある市場といえます。
データで見る強さと揺らぎ
- 日本におけるITエンジニアの正社員転職求人倍率は 10倍超 に達しており、ある調査では 11.6 倍という数値も報告されています。
- 有効求人倍率は全体平均が約 1.58 倍であるのに対し、IT関連職は 3.19 倍 と高水準です。
- 直近では「求人数の微減」や「転職希望者数の増加」により、やや買い手市場寄りへ傾く可能性が指摘されています。
- 50代以上の転職希望者も増加傾向にあり、年齢層の幅が広がってきています。
- DX(デジタルトランスフォーメーション)、クラウド、データセンター投資といった要因により、国内IT市場そのものは拡大基調にあります。

大きな需要はあるものの「スキルのミスマッチ」や「年齢層の多様化」「選別の厳格化」が同時に存在しているのが、現状のITエンジニアの転職市場と言えそうですね。
求められるスキルや方向性の変化
- AI / 機械学習 / データ領域:生成AIやデータ活用に携わる人材は特に重宝されています。
- クラウド / SRE / DevOps:大規模システムにおける可用性や運用効率を担える人材が強く求められています。
- セキュリティ:脅威の増大に伴い、専門的な知識を持つ人は希少価値が高まっています。
- IoT / 組み込み系:特定ドメインでの技術力は依然として根強い需要があります。
- スペシャリストとジェネラリストのバランス:深い専門性だけでなく、ある程度の幅と柔軟性を持つ人材が評価される傾向があります。

年齢に関係なく、専門性が活かせる転職市場になりつつあるようですね!
強みを持つ人と苦戦する人の差が際立つ
市場全体が活況であっても、誰もが好条件で転職できるわけではありません。その差を生む要素について整理します。
有利に働く要素
- 具体的な実績:成果を具体的な数字で示せる人は有利です。
- 汎用性と適応力:新しい技術をキャッチアップできる力は大きな武器です。
- コミュニケーション力やドメイン知識:ビジネス側との橋渡しができるエンジニアは高く評価されます。
- 希少性スキル:高度なセキュリティや高負荷システム設計などは代替が効きにくい強みとなります。
- 統括的な経験:マネジメントや全体設計を担える人は年齢層が上がっても有利です。
苦戦しやすい要素
- トレンド技術へのキャッチアップ不足
- 実務経験が浅い、成果を言語化できない
- コミュニケーション不足やドキュメント力の欠如
- 技術だけに偏りビジネス視点が弱い
- 外の環境変化に適応できていない
注意すべきポイント
- 選考スピードの速さ:良い案件はすぐに決まります。準備不足は致命的です。
- ミスマッチ採用のリスク:仕事内容や文化と合わないと早期退職につながります。
- 市場の不確実性:景気やAIの自動化による淘汰リスクがあります。
- 条件格差の拡大:上位層は好待遇ですが、中堅層以下は競争が激化しています。
- 年齢の壁:キャリア中盤以降はマネジメント力や統括力がより重要になります。
まとめ
ITエンジニアの転職市場は「強い需要に支えられたチャンスの場」である一方、「準備不足な人には厳しい試練の場」でもあります。
転職で成功するためには以下が鍵です。
- 自身の強みを言語化し、成果を数字で示す
- AIやクラウド、セキュリティといったトレンド技術を学び続ける
- 複数のエージェントを活用して情報を幅広く収集する
- 書類やポートフォリオを常に最新に更新する
- 条件交渉のスキルを磨く
FQA(よくある質問)
- Q40代でも転職は可能でしょうか?
- A
はい、可能です。ただし、成功する転職にはいくつかの条件があります。これまで積んできた経験を「価値」として相手に伝える力や、転職先の市場ニーズとの整合性をつくる準備が重要になります。年齢がハードルになる場面もありますが、それを乗り越える戦略さえあれば、新しい道は開けます。
- Q年齢がネックになるという話は本当でしょうか?
- A
実際にそのような懸念は存在します。人件費や変化対応力、技術トレンドへの追随力といった要素で、企業側が慎重になるケースがあるのは否定できません。しかし、最新技術を学び続けている証拠を示す、変化への柔軟性を言動で伝えるなどすれば、年齢を“リスク”でなく“強み”に変えることもできます。
- Q技術力が追いつかないように感じます。どうすればよいでしょうか?
- A
技術進歩の速さに戸惑うことは当然ですが、学び方を変えることで対応可能です。まず基礎理論やドメイン知識を整理し直し、アウトプット中心の学びを取り入れると有効です。技術ブログやオープンソースへの寄与などを通じて、自分の理解を深めながら他者にも示す形にできます。得意分野を中心に据えつつ、コミュニティや勉強会で刺激を受けることも助けになります。
- Q専門性を深めたほうがよいでしょうか、それとも守備範囲を広げたほうがよいでしょうか?
- A
どちらが正解とは言い切れません。専門性を深めることで武器を持てますが、変化の激しい時代にはリスクもあります。一方、守備範囲を広げれば適応力は上がりますが、突出しにくくもなります。理想は、専門性を“軸”にしつつ、必要最低限の守備範囲を持つバランス型を志向することです。
- Q現場の技術を続けるべきでしょうか、あるいはマネジメントに回るべきでしょうか?
- A
正解は個人の適性や志向によります。技術を追い求めたいなら現場を続けるのも良い選択肢ですし、人を育てたい、組織に関わりたいと感じるのであればマネジメントも道になります。重要なのは、どちらを選ぶにしても長期的な視点でプランを持ち、途中で選択を変えても後悔しないように設計しておくことです。
- Q転職を考えるなら、いつ頃から準備を始めるべきでしょうか?
- A
はい、そのリスクはあります。特に、専門分野を変更する場合や、規模の小さい企業に移る場合、あるいは条件の優先順位を変えた場合には年収減少が発生しやすくなります。ただし、このリスクをただ怖がるのではなく「成長投資」「将来的リターンを目指す一手」として受け入れる視点をもっておくと、判断の質が変わります。
- Q転職によって年収が下がるリスクはありますか?
- A
はい、そのリスクはあります。特に、専門分野を変更する場合や、規模の小さい企業に移る場合、あるいは条件の優先順位を変えた場合には年収減少が発生しやすくなります。ただし、このリスクをただ怖がるのではなく「成長投資」「将来的リターンを目指す一手」として受け入れる視点をもっておくと、判断の質が変わります。
- Q未経験領域へのチャレンジは無謀でしょうか?
- A
難易度は高いですが、無謀ではありません。ただし、リスクと準備は綿密にすべきです。市場ニーズやスキルギャップを見極め、転換期の収入変動や学習負荷を許容できる計画を立てて、段階的に入り口を小さくしながら進む方法が現実的です。
- Q40代で歓迎されやすい企業・プロジェクトにはどのような特徴がありますか?
- A
経験と技術力を重視する企業、レガシー刷新やDX推進といった実績重視のプロジェクト、安定性を重んじる金融・インフラ・医療業界などには可能性があります。またベンチャーでも「経験者を戦力化したい」と考える企業は、40代の技術者を歓迎することがあります。
- Qセカンドキャリアや定年後を見据えるべきでしょうか?
- A
はい、ぜひ見据えておくべきです。40代以降は、働き方・健康・ライフスタイル・家族との時間などを含めた包括的なキャリア設計が求められます。技術コンサル、教職・講師、技術顧問、副業など、経験を活かせる選択肢を複数持つことが、将来の安心感につながります。