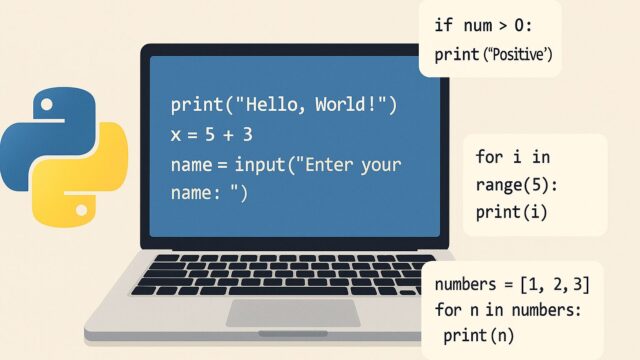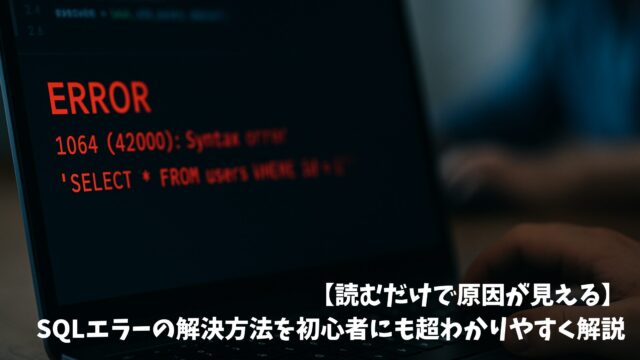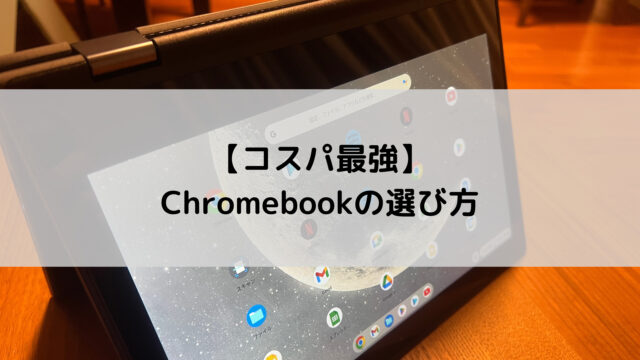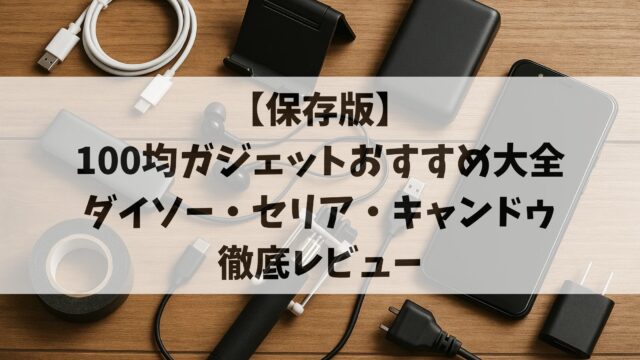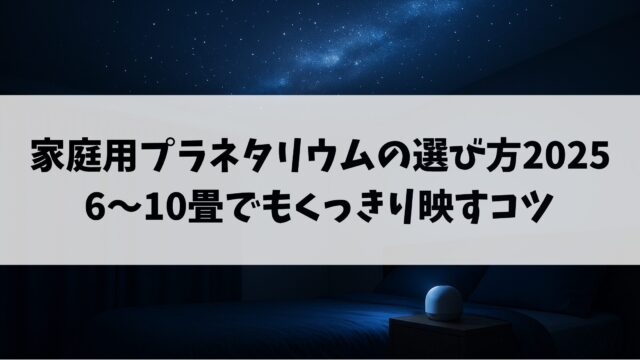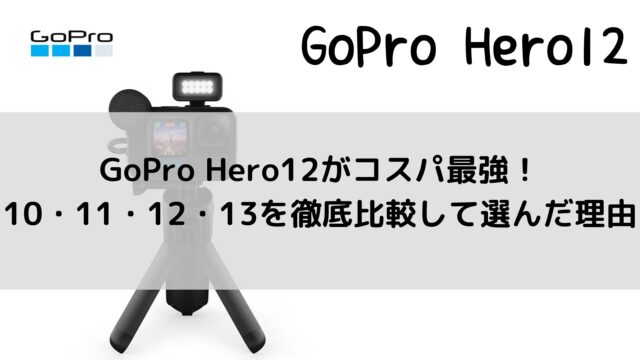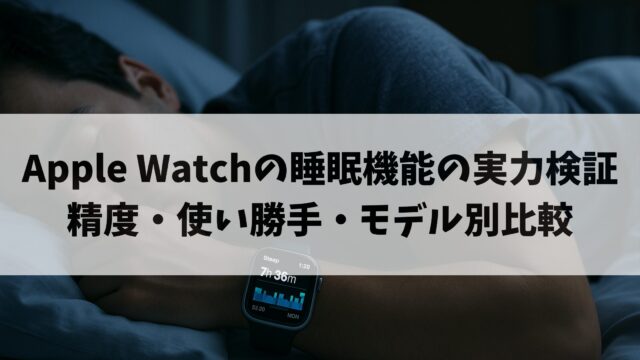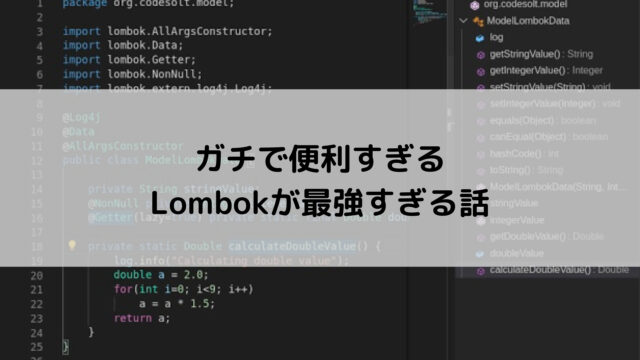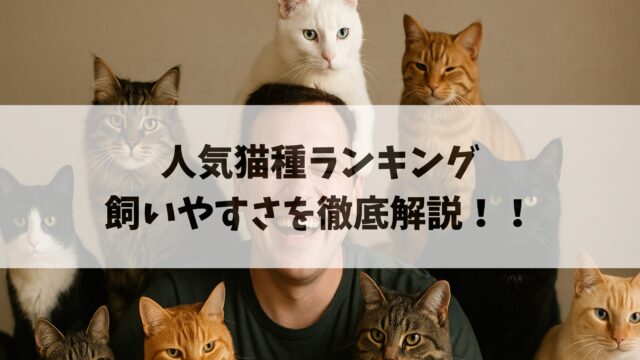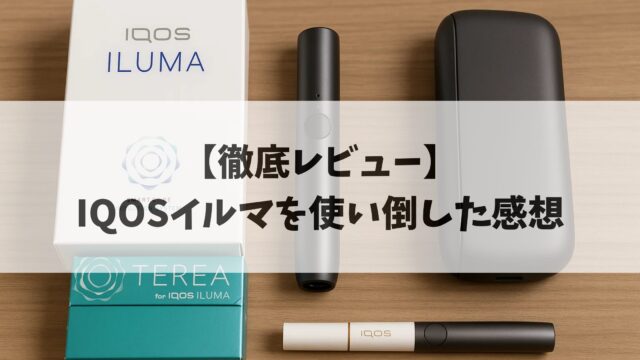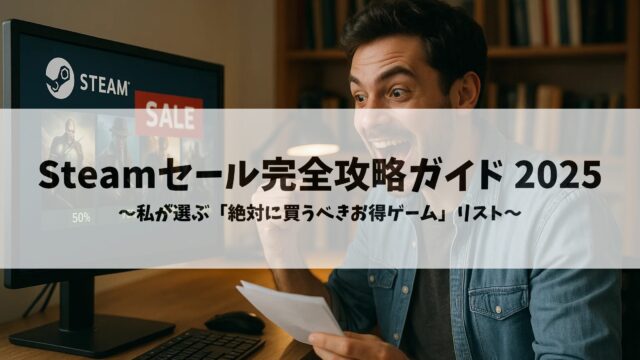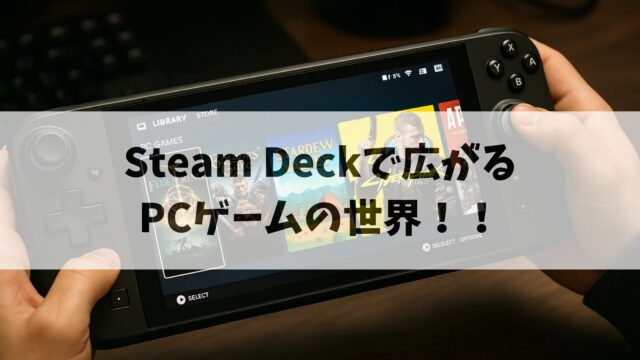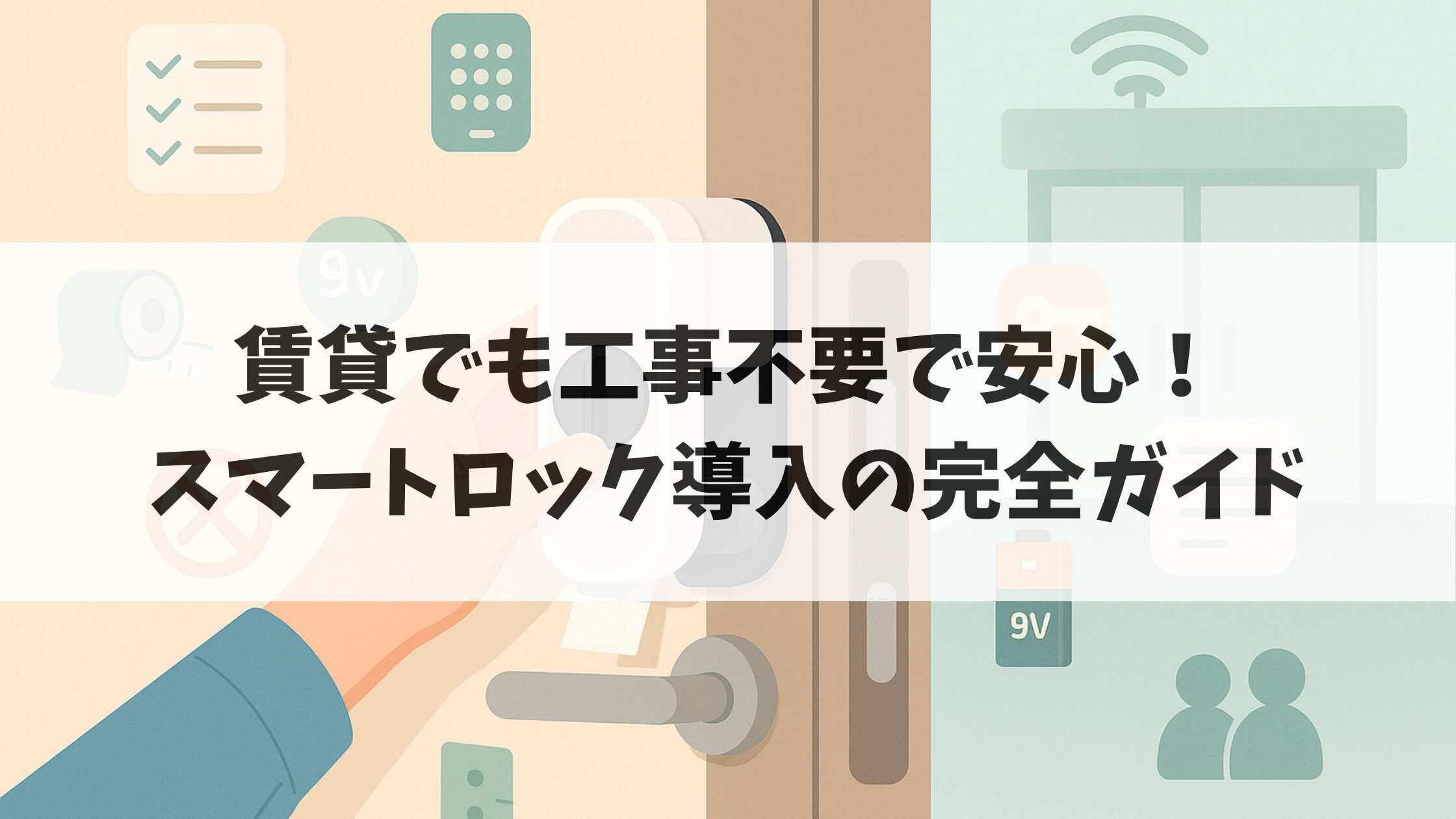賃貸でも本当に大丈夫?
賃貸でもスマートロックは“条件付きでOK”です。
条件は【工事不要=両面テープ固定/穴あけなし/室内側だけの見た目変更/外せば元どおり】の4点を満たすこと。
原状回復は「温め→糸やフロスでスッと切る→リムーバーでのりを拭き取る」で対応できます。
オートロック物件は要注意です。当然、エントランスは共用設備なので、住戸側スマートロックでは開きませんので注意しましょう。
今日のゴール
賃貸OKチェックリスト
導入前にここをサクッと確認します。全部「はい」なら進めてOK、ひとつでも迷ったら申請か相談で安全運転いきましょう。
原状回復3点(固定方法・見た目・撤去方法)

この3点がOKなら「外せば元どおり」間違いなし。迷うところは写真で記録しておきましょう!
ルール確認(管理会社/共用部/外観)
取り付け可否のセルフ診断
やることは「測る→当てる→動かす」の3ステップだけです。型紙PDFと紙メジャーがあれば、いまこの場で“付く/付かない”の見通しが立てられるよ。数値はメーカーごとに差があるので、ここでは“測り方の型”を押さえましょう。
サムターンの形・厚み・高さの測り方
まずは相性チェックの心臓部。サムターン=室内側のつまみのこと。
A4で印刷した型紙、紙メジャー(巻尺でもOK)、定規、ペンを使って計測していきましょう。
- 型紙の“サムターン枠”に合わせて形状を判定(つまみ型/羽根型/ボタン押し式)。
- 厚み=つまみの最も厚い部分、高さ=ドア面からつまみ中心まで、幅=左右最大を測る。
- つまみ中心からドア枠までの距離もチェック(本体が回るクリアランス用)。

型紙の許容範囲に全て収まれば“物理的にいける可能性高め”。ボタン式は押し込み量や段差で不可のことがあるので注意しましょう。
扉厚・バックセット・ドア枠との距離
ここでは“本体が置ける平面があるか”を見ていきます。
- 扉厚をドアの上端か側面で測る。
- ドア端→サムターン中心までを定規で測り、型紙の推奨レンジに入るか確認。
- サムターン周りに“台座が貼れる平面”があるかを目視(段差・丸み・窓枠に注意)。

ドアを全開・半開にして、取っ手や枠と本体がぶつからないかもイメージで確認しておきましょう。
ドアクローザー・ドアチェーンの干渉確認
最後は“動かして”ぶつからないかの確認をします。
- ドアをゆっくり開閉し、サムターンの回転軌道にクローザーの腕・ネジ・チェーン座が入ってこないか観察。
- 上下左右に本体の想定位置を手で当て、扉や枠に干渉しないかを確認。
- 金属粉や油汚れは後で粘着を弱らせるので、取り付け面はアルコールで拭けるかもチェック。
セルフ診断のまとめ
- 型紙に収まる
- 台座の平面あり
- 開閉で干渉なし
- “取り付けOK”の可能性高
どこかで引っかかったら、貼り位置の再検討 or スペーサー検討 が必要です。
これだけ見れば迷わない!
開け方の違い(アプリ/暗証番号/IC/物理鍵/ハンズフリー)
玄関の“開け方”はライフスタイルで選ぶのがコツです。迷ったら下の早見表でサクッと判断してください。
| 開け方 | 向いてる人 | 注意点 |
|---|---|---|
| アプリ | 大人中心 | 電波×の時はPINや鍵に切替 |
| 暗証番号 | 子ども/来客多め | 定期的にコード更新 |
| IC | 家族で共用 | 落としたら即失効 |
| 物理鍵 | 全員 | 最後の保険として常備 |
| ハンズフリー | 荷物多い人 | 誤解錠対策の設定必須 |
オートロック対応・解錠ログ・期限つき合鍵
“できること”を機能で整理します。

①ログが見たいか
②一時合鍵を配るか
③エントランスは管理ルールに従う
の3点で必要機能を決めていきましょう。
Wi-Fiハブ有無と外出先操作/Bluetoothだけで使える範囲
スマートスピーカー連携と“声で開けない”安全設定
音声連携は便利ですが、解錠は安全が最優先です。

音声認識は万が一のことを考えて、安全設定にしましょう。
①解錠はPIN必須or無効
②家族ごとに権限分け
③施錠の音声コマンドだけ許可
電池種類・寿命・交換サイン/非常時の開け方一覧
当たり前ですが、電池は“切れる前に替える”ことが重要ですね。
ペルソナ別おすすめ構成
一人暮らし:貼るだけ+ハンズフリー最優先
移動多めで手ぶら派なら、両面テープ固定+自動施錠+ハンズフリーで“帰宅→そのまま入れる”を実現してみましょう。通知は最小限でOKです。
子どもあり:キーパッド/ICで“鍵いらず”
スマホなしでも入れる構成が最強です。キーパッドやICタグに個別IDを割り当て、帰宅ログで見守り対応もできます。
ルームシェア:入室時間制限とログ重視
“誰がいつ入ったか”を記録することで揉め事を防ぎましょう。メンバーごとに権限と時間帯を分け、退去者の権限はワンタップ停止できるようにしましょう。
配達が多い:ハブで一時合鍵&遠隔解錠
外出中の受け渡しが多いなら、Wi-Fiハブで遠隔操作&“回数・時間限定”の合鍵を使い分けます。オートロックの入口は別設備なので、基本は玄関側での受け渡し前提で考えましょう。
取り付け〜撤去の手順書
位置決め→脱脂→貼り付け→校正→試運転
まずは、型紙・紙メジャー・アルコール(無水 or 消毒用)・不織布・マステ・圧着ローラー(なければ指の腹)・予備電池を準備しましょう。
- 位置決め:型紙を当ててサムターンの回転クリアランスを確認→本体の“輪郭”をマステでガイド化。取っ手/枠/チェーンに当たらないか開閉でチェック。
- 脱脂:取り付け面をアルコールで円を描くように拭き、完全乾燥(水分/油分ゼロが命)。
- 貼り付け:剥離紙を半分だけ剥がし、ガイドに沿って仮置き→位置OKなら全剥がし→30秒以上しっかり圧着。室温はなるべく20℃前後、貼付後24時間は強い衝撃NG。
- 校正:アプリで回転角と左右を学習→自動施錠時間・ハンズフリー感度・通知を設定→家族ユーザー/コードを発行。
- 試運転:施錠/解錠を10回テスト(ドア開/閉の両方)。引っかかりがあれば位置を微調整し再校正。
- 【注意】カッター/金属ヘラは使わない。粘着のコツは「脱脂・圧着・養生」。

剥がし方(糸/フロス・リムーバー・跡残りゼロのコツ)
デンタルフロス(または釣り糸)・ドライヤー(温風)・粘着リムーバー・不織布・プラカードを準備します。
- 温め:本体とテープ周辺をぬるめの温風で均一に温め、粘着を柔らかく。
- 糸でカット:壁と本体の“間”に糸を通し、左右に小刻みに動かして切る(糸はこまめに交換)。
- 残のり除去:リムーバーを少量なじませ、プラカードでやさしくこそげ→不織布で拭き上げ→最後にアルコールで仕上げ。
予算の全体像
まず“いくらかかる?”をざっくり見える化します。価格は季節セールで上下するので目安としてとらえてください。
相場(税込・概算)
合計の目安(構成別)
管理会社への申請テンプレート
コピペOKです。〔 〕内だけ差し替えて使ってください。室内側・工事不要・原状回復できる前提での文面となってます。
件名:〔物件名・部屋番号〕/室内側スマートロック設置の事前申請(工事不要)
〔管理会社名〕 御中
契約者:〔氏名〕 物件:〔物件名〕〔部屋番号〕 契約番号:〔任意〕
連絡先:TEL〔 〕/Mail〔 〕
1.目的
防犯性と入退室管理の向上のため、住戸玄関「室内側」にスマートロックを設置したく申請します。
2.設置場所・外観
専有部:玄関ドア「室内側」のサムターン周辺のみ。
共用部・外観(ドア外側・枠・集合玄関)の加工・変更は一切行いません。
3.固定方法(工事不要)
両面テープのみで貼り付け。ネジ止め・穴あけ・配線工事は行いません。
4.撤去方法(原状回復)
退去時は「温風で軟化 → 糸/フロスで切離し → 専用リムーバーでのり除去 → アルコール拭き上げ」を実施し、跡残りなく原状回復します。
5.原状回復の責任
万一、跡や損傷が発生した場合は、契約者負担で補修します。
6.設置・運用期間
設置予定日:〔YYYY/MM/DD〕 運用期間:退去まで(更新時に継続可否を再確認)。
7.非常時対応
電池切れ等の不具合時は速やかに復旧します。緊急連絡先:〔TEL〕
物理鍵は常時有効で携行し、必要時は管理会社様の入室立会いに協力します。
8.添付資料(A4各1枚)
① 設置予定位置の写真(室内全景1・接写2)
② 撤去手順メモ(上記手順の図解)
③ 製品仕様の抜粋(固定方法・電源・非常時の開け方の記載箇所)
④ 型紙/採寸メモ(サムターン寸法・扉厚 等)
以上、ご確認のうえご承認をお願い申し上げます。
承認欄:________(管理会社) 承認日:__年__月__日
よくある質問
- Q冬場に反応が鈍い/開かない
- A
- Qアプリがつながらない(Bluetooth/ハブ)
- A
- Q自動施錠が効かない/遅い
- A
- Q本体が浮く/粘着が弱い
- A
- Qハンズフリーが誤解錠する/反応しない
- A
- Qキーパッドが反応しない/PINエラー続発
- A
- Q電池がすぐ減る
- A
- Q回らない・ギギッと引っかかる(トルク不足)
- A
- Q解錠ログや通知が来ない/遅れる
- A
- Qエントランス(共用オートロック)が開かない
- A